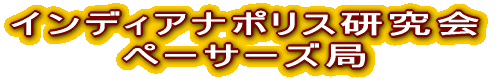

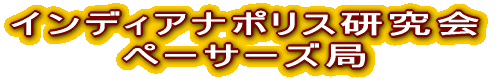


| Conference Finals |
東地区決勝 第1戦第2戦 @MSG |
ペイサーズvsニックスのカンファレンスファイナルじゃ〜〜〜〜。 っつても、ユーイングもスタークスもデレック・ハーパーもオークリーもチャールズ・スミスもメイソンもスプリーウェルもマーカス・キャンビーもラリー・ジョンソンもアラン・ヒューストンもいないよ。あれから25年後の話だからね。 あっ、そうそう、ニックスで最も重要な人間、スパイク・リーもいなかったな。ついに出禁。ニューヨーク追放。国外追放。地球追放。太陽系追放。銀河系追放。宇宙追放。現世追放。来世も追放。存在の消去。唯一の友達レジさんは会場に姿を見せてたのにね。まっ、どーでもいいけど。 とまあ、追憶と興奮の2025イースタンカンファレンスファイナルについてのレポートを早速書きたいのであるが、その前にプレイオフについての感想をいくつか。 プレイオフを数試合、というか数十分間ほど、うつらうつらしながら、観戦したのであるが、まず最初に思ったのは、「プレイオフはさすがにインサイドを強調すんだな。」って事である。 レギュラーシーズン同様、3P大会になるのかと思いきや、意外なほどインサイドを強調してた。理由は分からん。ただ、惜しむらくは、インサイドを強調しても、ペイント内のオフェンススキルを持っている選手が、私の見た限り、私のうつらうつら見た限り、どのチームも皆無に等しいので、あまり意味や有効性を感じなかった。あれだったら、レギュラーシーズン同様、3P大会をしていた方が良かったように思う。 で、実際、3Pの成功率や成功数が得点や勝利に直結してた。 その反映どうか知らんが、点差が付く試合が多いようにも感じられた。前半終了時とか第3クォーター終了時に30点差40点差がついて、そのまま試合が終了してしまうケースが多いように感ぜられた。NBAのゲーム、とりわけプレイオフになると、私の見ていた頃は、基本接戦で、試合中盤くらい大差がついていたとしても、不思議なくらい、いや八百長が疑われるくらい、試合終盤には接戦になっていたものである。これはちょいと意外だった。八百長禁止したの。マジメにやってんの。 あと、凡ミスが多いようにも感ぜられた。パスミスとかドリブルミスのような初歩的なハンドリングミスが目立った。これもかつては見られなかったものだ。ワンマン速攻のシュートミスも目立つ。 このへんは「ゆとり世代」「Z世代」って事なのかな。あんなのはコーチが怒鳴れば消せるミスである。 これらに関連してかどうかは分からんが、全体的に「もっさり感」は否めない。かつてのNBAの方が速く・高く・強かったと思う。いや、強さはさほど変わらないかな。ただ、速さと高さは劣っているように感ぜられた。アジリティとジャンプ力はかつての選手の方が上だと思う。 そういった諸々の点を鑑みても、ヨーロッパのバスケットボールによく似ていると思う。90年代00年代のヨーロッパのバスケットボール、ヨーロッパのバスケットボール・プレイヤーがこんな感じだった。これがバスケットボールの進歩なのか退歩なのかはよく分からん。 あと、もひとつ気になったのが、どこぞのゲームで第7戦残り2分20点差で主力を引っ込めちゃった事である。まあ、確かに、来季もあるので「ケガをするかもしれない」から、主力を引っ込めるのは合理的な判断なのかもしれない。 でも第7戦でしょ、プレイオフでしょ、「Win or Go Home」でしょ。わずかな可能性に賭けて、全力を尽くすべきじゃないの。それこそ「8points in 9seconds」があるかもよ。いや、実際、あったんだし。諦めるの早すぎじゃねーの。 こういうのは、NBAに限らず、他のプロスポーツにおいても昨今よく見かける光景だけど、こういう事をするんだったら、それこそ「コールドゲーム」にして、残り時間を余して試合終了にしてしまえば良いと思う。「負けてる側の監督」が「敗北宣言」して、そこで試合終了にしろっつの。将棋の「投了」や囲碁の「中押し」みたいなもんである。ベンチメンバーにだって来季はあるし、「ケガをするかもしれない」んだから。諦めたとこで試合終了にすべきだと思う。まさしく、「諦めたら、そこで試合終了ですよ。」。 愚痴はそれくらいにして、熱狂と興奮のマジソン・スクエア・ガーデンに話を移そう。 結果、2連勝〜〜〜〜〜〜。 いや、ビジター2連勝はデカいよね。 で、気になった選手についてちらほら。 まずはミッチェル・ロビンソン(すっげー、普通な名前!)。 ペイサーズファンなのに、ニックスの選手が気になってしまうとは何事だって感じであるが、気になってしまったのだから仕方がない。 NBA復帰一発目の記事で、「オークリーやロッドマンみたいな選手は、最近のNBAではお払い箱だ。」みたいなことを書いたのであるが、いたよ、ロッドマンみたいな選手が、オークリーみたいな選手が。リバウンド特化型選手が、スクリーナー特化型選手が。 今軽くスタッツを調べてみたのであるが、7年目で1試合平均25分ほど出場してるのであるが、なんとここまで3Pアテンプト0。3P未経験だよ(無論、エロい意味はない。いやん、ス・ケ・べ。)。今時いるんかい、そんな選手。しかも、キャリア通算のフリースロー成功率が52.2%だよ。俺のがマシだよ。俺のがエロいよ。 しかも、誕生日が1998年4月1日。言われてんだろうなあ。「お前が生まれたのはウソだ。」とか。お誕生会を開いてもらえないタイプ。「え、あれウソだと思ってた。」。 日本だと、1日ずらして「4月2日生まれ」にしちゃうんだよね。今は病院やお役所がうるさいのかな。そうそう、桑田真澄が4月1日生まれ。なんか、親に考えがあったんだろうけど。桑田本人は「この日に生まれて苦労した」とは語ってるけどね。まあ、1968年4月1日生まれだったからこそ、桑田はプロ野球選手になれたのかもしれないし、なにより「KKコンビ」が誕生できたのだから、これで「良し」とするか。 欲しい。いや桑田じゃなくてミッチェル・ロビンソン。こいつは欲しい。久々に「欲しい」と思わせる選手に出会った。実際、ロビンソンがオン・ザ・コートの時、ペイサーズは苦労してるし。私だったら、スターターで使う。 次はいよいよペイサー。ハリバートン。第1戦のヒーローである。 今回初めて、1試合つうか2試合丸々見たが、まあ、なんつーか、ケニー・キトルズとかロン・ハーパーとかミッチ・リッチモンドとか、そんなタイプの選手と見た(譬えが古いぞ。覚悟しろ。)。内でも外でも点が取れて、それなりにパスもサバけるガード。エースを任せる能力はあるが、1試合平均は20点前後、そんな感じの選手である。ガードとしては、セカンドグループのトップみたいな位置付け。トップグループはレイ・アレンとかアレン・アイバーソンとか、そういう人達である。彼らの次のクラスのトップみたいな感じ。マイケル・ジョーダンは、そのトップグループの更に更に上。神グループ。グループっつっても一人しかいないけどな。神だけに。 また、レジさんは、彼等とはタイプが違うので、クラスというよりはカテゴリーが違うという感じ。レジさんのグループにはアラン・ヒューストンとかクリス・マリンとかが属している、そんな感じ。それなりに内でも得点できるが、基本的には外特化型みたいな感じ。 で、ハリバートンに話を戻すが、この手のタイプは、勿論エースも務まるけれど、どっちかつうと、オフェンスのセカンドオプションとして生きるタイプ輝くタイプだと思う。「エースの反対側」で活きるタイプだと思う。ロン・ハーパーのキャリアはその典型だし、ケニー・キトルズも同様だろう。ミッチ・リッチモンドのキャリアの苦しさは、ルーキーイヤーを除いて、彼がエースを張り続けなければならなかった点にある。ひとつ間違えれば、いや間違いじゃなくて、上手くボタンを掛ければ、ロン・ハーパーのようなキャリアもあった筈である。 という訳で、一ペイサーズファンとしては、ハリバートンに代わる、というかハリバートンを超えるオフェンスのファーストオプションが欲しい。さすれば、王朝も夢ではない。それが誰なのか、何なのかは、全然分からない。とりあえず、それがミッチェル・ロビンソンではない事だけは、はっきり分かる。明々白々である。自明である。 んなぐらいかなあ。「いや、2人の選手評をしただけやん。」と突っ込まれそうであるが、さすがに10年振りなので分からん事が多すぎる。も少し、色々知ってからね。 でも、第2戦、勝利した瞬間は良かったなあ。マジソン・スクエアがシーンとしてた。「ザマーッ」って思ったね。ガッツポーズしちゃった。いやあ、良かった。スカッとした。俺の中から熱い何かが甦ってきた。 2025/5/25(日) |
| 東地区決勝 第3戦〜第5戦 |
フアン・ソトが批判されている。 契約の詳細が分からないので、断言は出来かねるが、もしも、この15年契約が完全保証されているのなら、そりゃ、ヤル気なくすよね。ヤル理由がないよね。年齢的に考えても、これが最後の契約だろうし、契約終了後は事実上引退であろうから、そりゃ、ヤル訳が無い。練習なんてする訳が無い。私だって、やらない。これでマジメに練習するのは、大谷のような異常な野球好きだけであろう。ヤル気デネーーー。 強いて「ヤル理由」を挙げるとしたら、ファン等々の批判悪口だけであろうが、そんなもんでお腹が減る訳でもない。気の弱い人ならお腹が痛くなるぐらいであろうが、そんなのだって、せいぜい一年である。人の噂も何とやら、ではないけど、人の批判悪口を1年以上も続けられる訳が無い。いずれ、飽きてしまうであろう。あるいは、新しい批判悪口の標的を見つけるだけであろう。実際、レンドーンへの批判悪口は影を潜めている。 また、その仕事が人の命に関わるようなもの、例えば医師とか消防士、バスやタクシーの運転手等々なら、「ヤル気」とは別にやらざる得ないだろうけど、ぶっちゃけ野球なんて命に関わる仕事ではない。それどころか、この世に必須の仕事でもない。無くても全然誰一人困らない仕事である。いや、むしろ「フアン・ソトのヤル気の無さ」は、ヤンキースの関係者やファン等々を始め、メッツの関係者やファン等々以外にとっては福音である。一服の清涼剤ですらある。 長期契約は考え物だよね。 つか、私がGMだったら、「複数年契約」は絶対認めん。「単年契約」だけで戦う。「複数年契約が欲しかったら、がんばんな。ただし、ウチはやらない。ヨソと契約しな。ウチはそのチャンスを与えるだけだ。」。で、ギラギラした奴だけで戦う。でも、ジョーダンとかマニングとか大谷とかだったら、複数年しちゃうかなあ〜〜。意志薄弱。 ちなみに、ソトの陰に隠れてはいるが、ゲレーロJr.も、詳細は不明であるが、昨オフ14年契約。んで、ここまで2割8分、8本塁打。コメントは差し控えます。 次は、それと対照的かどうかは分からぬが、野沢雅子の話。 「野沢雅子がアンパンマンどうのこうの」という見出しだったので、「高齢を理由に野沢雅子が『アンパンマン』を降板した」のかと思ったら、逆に「就任」してた〜〜〜〜。まだ、仕事増やすのかよ〜〜。てめえ、いつになったら死ぬんだよ(不謹慎)。おめえ、老後がねーのかよーー。 いやまあ、実際、野沢雅子の「全仕事」を知っている人がいたら、「ヲタク」というより「狂人」だと思う。本人も知らんからな。三つぐらいしか憶えてないからな。孫悟空も忘れてっからな。その昔、「岸田森全仕事」というような本があって、私は即買いしたけれど、「野沢雅子全仕事」というような本があったら、即買いすると思う。まっ、不可能だろうけどな。 でも、野沢雅子って、ホント大昔から声優してっからな(悟空風に)。古いアニメ、それも白黒テレビ時代のアニメにも出てくるからな。マジでびっくりする。白黒のアニメなんて、今の若い人は知らないでしょう。いや、私だってリアルタイムじゃないよ。 石田国松も野沢雅子かなと思って、今調べてみたら、こちらは大山のぶ代だった。私が好きなのは、ガンバかな。鬼太郎や鉄郎はちょっと違うと思う。鉄郎はともかく、鬼太郎は男声がやる役だと思う。 「オッス、オラ悟空」。これ、ドン・キホーテと並んで、日本人のトラウマだよね。二大耳から離れない音声。 さて、話は変わって、「日産」である。 「日産」の苦境について、様々な批判が飛び交ってる。「ああすりゃ良かった」「こうすりゃ良かった」「こうすればいい」「ああすればいい」等々である。 みんな詳しいな。「日産」の話だったら、多くの日本人が色々な事を云うのも分からんではないけれど、今まで、この手のニュースで一番驚いたのは「ウクライナ戦争」。ウクライナとロシアについて何らかの意見を持っている日本人が沢山いることに私は驚いた。 私は「ウクライナ」についての知識は皆無である。何も知らない。ちょっと話が逸れるが、サッカーの国際大会で「ジョージア」という国が参加しているのに驚いた事がある。「ジョージア州のサッカーチームが国際大会に出場してんだな。」なんて呑気な事を思ってた。後に知ったのであるが、「旧グルジア」。 ロシアについては、さすがに知識が皆無という事はない。つっても、知ってる事と云ったら、エカテリーナ二世とかレーニンとかスターリンとかゴルバチョフとか、あるいはプーシキン、ゴーゴリ等々の文学者くらい。他の知識はほぼ皆無に等しい。まして、ロシアとウクライナの政治情勢なんて何も知らん。その戦争の是非を断じるなんて、とても出来ん。みんな物知りなんだねえ。 話を「日産」に戻すが、そうした「日産」への種々の意見の中に、「こんなクルマを作れば、売れた」「あんなクルマを作れば、売れる」みたいなものがある。 いや、すごいねえ。俺、そんな事絶対言えんわ。クルマでなくても、「あめー、絶対必ず売れるものを一ヶ月以内に考えてこい」なんて命令されたら、「ウワーーーーーー」ってなって、逃げ出すわ。それも日本からではなく、宇宙から、いや、この世から逃げ出すわ。 そもそも、私はこの手の「予想」には全く自信が無い。「何が売れるのか」全然分からない。以前、どこかに書いたけれども、「ミニ4駆」と「セーラームーン」という超絶メガヒット商品(作品?)を「全然売れない」と予想していたし、そこまで大きくなくとも、この手の予想は私は大概外れる。 つか、そもそも、「私の好きなモノ」は大概人気が無い。特に「食べ物」。数年前、私はアサヒの「クラフトコーラ」にドハマりしてたけど、あっという間に「終売」。店頭や自動販売機から消えた。一時は、これをガブ飲みしていて、血糖値が上がってしまったくらいである。そういった意味では、この「終売」は良かったのかもしれん。 いや、良くね〜〜〜〜〜。俺の味覚は間違ってね〜〜〜。クラフトコーラはコカ・コーラやペプシより旨いんじゃ〜〜。間違っているのは、オマエらの方じゃ〜〜〜。 てなことが多い。特に「食品」には多い。えっ、私の舌がおかしいの。 という訳で、私にはこの手の「売れ行き予想」や「絶対必ず売れる商品開発」は絶対無理なのであるが、「絶対必ず売れる」なんて、誰にも分からんよね。 「あらゆる商売はギャンブルである」という命題の最終的な根拠は「打順論」で書くつもりだけど(いや、必ず書きますよ。)、「絶対必ず売れる」が不可能であることは、ちょっとした背理法で簡単に説明が付く。 仮に、「絶対必ず売れる商品」があると仮定する。とすると、全ての人が「絶対必ず売れる商品」を作るであろう。なにしろ、「絶対必ず売れる」のだから。作らないと損しちゃう。 で、全ての人が「絶対必ず売れる商品」を作ったら、一体それを誰が買うのであろう。なぜなら、全ての人が「絶対必ず売れる商品」を持っているのだから。それも「売る」程な。 以上、証明終わり。Q.E.D。 これを「極論だ」として反論する人がいるかもしれないけど、全てとは言わぬが、大概のものが売れなくなる理由は大概これである。それこそ、「クルマ」なんていう商品はその最たるものであろう。 まずは20世紀前半、欧米でモータリゼーションが起こる。そこでメルセデスやルノー、ジャガー、あるいはビッグ3がブイブイ、いやブーブー言わす。それがしばらくすると、多くの欧米人が自動車を所有するようになり、欧米の自動車会社、自動車産業は苦しくなる。 それと入れ替わるように、20世紀後半、日本でモータリゼーションが進む。かつては金持ちかごく一部の趣味人くらいしかクルマを所有していなかったのが、いつしか一家に一台、一人に一台、そうして一人に複数台、クルマを所有するようになった。 私はともかく、私の親の世代だと、「クルマを買う」というのは、ちょっとした街の噂になったものである。「○○さんのお父さん、クルマ買ったらしいわよ。」「じゃあ、今度乗せてもらいましょうよ。」。 今、クルマを購入しても街の噂にはならないだろう。せいぜい、「お隣さん、クルマ買ったよ。」「どうせ、軽だろ。黄色ナンバ、だっさ。」ぐらいなもんである。 で、その頃のビッグ3は日本の自動車産業の活況が羨ましく、色々とちょっかい出していた訳だけど、上記したような根本的な経済状況に抗える筈もなく、結局は歯ぎしりするのみ、ハンカチを咬んでキーってなるのみだった訳である。 そうして、21世紀にはいると、それが韓国、中国、インドへと移っていく。韓国はあっという間に飽和点に達してしまったが、中国インドあたりはまだ余白があるだろう。 家電やパソコン、スマートフォンにも似たような事が云えるであろう。 まあ、さすがに、上記の背理法のように「自身で作っているから、要らない」って事はないだろうけど、ある時期、ものすごく売れたものが、徐々に売れなくなっていくというのは、これが理由である。 これを避けるためには、「自分だけ、あるいは自分たちだけが作れて、時間とともに消失してしまう商品」というのが、「絶対必ず売れる商品」なんだろうけど、そんなものはなかなか無いよね。 「YKKのファスナー」がそれに近いものかもしれないが、手間がかかる割りには、単価が安いので、他が参入しないというだけなのかもしれない。 つう感じで、経営手腕や経営手法以前の問題として、経済構造的に「日産」、というか自動車会社全体の前途は暗いと思う。おそらく、総合自動車メーカーは世界で3社くらいになってしまうのではないか。 ひとつは「トヨタ」でほぼ決まりだろうけど、残る2社が「メルセデスベンツ」なのか「ルノー」なのか「ホンダ」なのか「現代」なのか「タタ」なのか、それは私には分からん。 他の自動車会社は、カテゴリーを特化していくしかないんじゃないかな。「スズキ」や「ダイハツ」は「軽」、「フェラーリ」や「マセラッティ」は無論「スーパーカー」、ビッグ3は「ピックアップトラック」と「ダッジ・チャージャー」等々。「いすゞ」は20年くらい前に「トラック」に特化してるしね。これは、今から思えば正しい経営判断だったと思う。 「ホンダ」や「マツダ」、「VW」や「メルセデスベンツ」は難しいとこにいるような気がする。「総合自動車メーカー」は茨の道だしねえ。「メルセデスベンツ」は「ロールスロイス」のような「超高級車路線」が正解なのかもしれん。かなりの思い切りは必要になるけどな。 で、問題の「日産」であるが、「GTR」と「Z」を全面に押し出して、「スーパーカー」路線に突き進むしかないんじゃないかなあ。「安物スーパーカー」(変な表現)ってとこは、今現在誰もいないから、案外その辺が狙い目なのかもしれない。「プアマンズ・フェラーリ」。いずれにせよ、経営規模はだいぶ縮小せざる得ないが。「電気自動車」も、厳しそうだしなあ。それに、儲けの出にくいジャンルだしね。「プアマンズ・フェラーリ」が、やはり正解かもしれん。俺の、当てにならない「売れ行き予想」だけどな。 「電気自動車」は「日産」に限らず、有力な選択肢かもしれないが、「電気自動車」つうのは、どっちかつうと、「自動車メーカー」ではなく「電機メーカー」の製品である。サスペンションとブレーキぐらいしか、「自動車メーカー」の技術は応用できない。 しかも、「機械を発動・制御する」のは「エンジン」より「電気」の方がはるかに楽チンチンである。実際、この世の多くの「機械」は「電気」で発動・制御されている。ガソリンエンジンで動くパソコンなんて聞いたことが無い。 実際、エネルギー問題、環境問題を抜きにしても、「自動車」の理想的な「発動・制御法」は「電気」なのだろうけど、それがなかなか難しいのは、やっぱり結局「電池、バッテリー」って事になろう。 そうして、以前どっかで書いたように、おそらく、真の意味で実用に足る「電池、バッテリー」は開発不可能だと思う。それを証明する科学者が出てくるだろう。実際、「電気自動車」そのもののアイデアは100年以上前、それこそ「ガソリン自動車」と同時期からあるにもかかわらず、なかなか実現しないのは、この理由があるからである。もっとも、それらを超えて、思わぬアイデアで「電気自動車」や、それを超える「自動車」を発明してしまう天才科学者が現れるかもしれないが。 で、ふと思ったんだけど、道路に電磁石的なものを埋め込んで、リニアモーターカー式の自動車にしてしまえば良いのではないだろうか。宙に浮いて走る自動車である。これならば、「電池、バッテリー」は不要、あるいは少量で済むと思う。完全な素人アイデアだけどな。 「日産」の今後はさておき、産業の個別化特殊化は、「家電」にも言える。というか、「家電」はとうの昔にそうなっとる。「総合家電メーカー」で頑張ってるのは、もはや全世界で「パナソニック」のみである。「GE」はとっくの昔に降りてるし、「東芝」は降りてる、というか、降ろされたし、「日立」は、もうほとんど「一般消費者向け」の「電化製品メーカー」ではなくなってる。つか、「GE」や「ソニー」なんて、もはや「家電メーカー」ですらない。 その他の「家電メーカー」は、先に挙げた自動車メーカー同様、特定ジャンル特化型である。「タイガー」や「象印」の「炊飯器」とか、「ダイキン」の「エアコン」とか、「リンナイ」の「ガス給湯器」(これは「家電メーカー」じゃないか)とかね。そのへんの舵取りを誤ったのが「シャープ」や「三洋」といったところなのかもしれん。 同じような事は、今をときめくコンピューター産業IT産業にも云える。かつて飛ぶ鳥を落とす勢いで売れたものが市場の飽和によって売れなくなっていき、売れたが故に巨大産業化した各企業が袋小路に陥るというパターンである。 数年前、私はWindows10からWindows11に移行した訳であるが、その移行作業をしながら、「めんどくせーなー。これも日本企業がやってたら、こうはならなかったのかな。」とも思ったが、一方で、「これは儲かんねえ商売だろうなあ。やっぱ、日本企業は手を出さなくて正解だったな。」とも思った。 確かに、世界中のほぼ全てのパソコンにWindowsのOSがインストールされている訳だから、それだけを考えれば、莫大な富を生み出しているとも云える。でも、30年前ならともかく、今や、買い替え、すなわちバージョンアップは10年に一度である。しかも、単価は3万円前後、卸値はそれ以下という事であろう。それでも、売りっ放しならまだマシだが、アップデイトがほぼ毎月である。厳密な収支はトントンなのではないだろうか。マイクロソフトは、本音を言えば、この商売から手を引きたいと思っているのではないか。今更そんな事、口が裂けても言えないけどさ。かなり無理した、謂わば「強奪した事業」だしね。 同じような事は他のコンピューター産業IT産業、アマゾン、グーグル、インスタグラム、旧ツイッター等々にも云えると思う。この手の産業(?)に日本企業が絡まなかったことを憤る人も多いが、ぶっちゃけ、たいした利益は出ていないと思う。 アマゾンはともかくとして、グーグル、インスタグラム等々は、基本的にユーザーが無料、タダで利用するものである。そこから利益は出ない。従って、広告料頼みになる訳だけど、これも、かつてのテレビのような広告効果は無い。なぜなら、市場は原則的に局地的だからである。インターネットの最大の強み・武器は「世界的」って事だけど、一般消費者の実際の売買は地方的局地的にならざる得ないのだから、「世界的」は広告にとって大きな強みにはならない。先に挙げた自動車で云えば、確かに一見国際的な商品だけど、実際は、アメリカで売れる車、日本で売れる車、フランスで売れる車、中国で売れる車等々、それぞれに異なる。従って、広告も局地的にならざる得ない。だったら、テレビやラジオの方が遥かに簡便だし効果的であろう。世界中で同時に売れた商品っていったら、ナイキのエアジョーダンぐらいしか思いつかない。 YouTubeとか見ていても、結構無理な広告がある。さすがに外国企業の広告は無いが、地方企業の広告はたまに見る。地方のリフォーム屋のCMとかである。いや、リフォームするにしても、お前の店には頼めんから。いや、頼まれても困るだろう。遠すぎて。 グーグルのAI、もっと頑張らんと。 また、アマゾンにしたって、あの「インターネット用市場」っていうのは、魚、野菜、古物等々、一般的な市場同様、本来、自治体や商業組合のような公的なものが運営するものであって、私企業が運営するようなものではない。手間ばかりかかって、ほとんど利益が出ないからである。サザビーズのように高級美術品なら話は別であるが、一般商品の市場を私企業が運営するのには無理がある。 実際、アマゾンの後を追うものが楽天ぐらいしかない(それも業態は微妙に異なる)のは、それがなかなか儲けの出ない、旨味の少ない商売だからであろう。ましてや、今やメーカーがインターネットで直接販売する時代である。ますます、アマゾンには怪しいものしか並ばなくなるであろう。 かくして、アマゾンやグーグルは、動画配信やスマートフォン等々、本業以外に手を出すのである。いや、出さざる得ないのである。本業が儲からないから。ちなみに、スマートフォンも今や完全に飽和状態である。10年後はともかく、20年後30年後には、時計や電卓同様、廉価版がダイソーに並ぶであろう。 とまあ、こんな風に考えると、この業界の大巨人であり、全ての母である「IBM」が、この業界、すなわち「一般向けコンピューター業界」から逸早く、それも驚くほど速く撤退したのも頷ける。彼らはこうなる事がはっきり分かっていたのだ。DOS/Vはイヤイヤながら作らされた感じであるけれど、その他のパソコン関連事業、OSでもSNSでもスマートフォンでも彼等ならお茶の子さいさい、開発・事業化できたであろうが、それをしなかったのは、それが銭にならない仕事、最近の言葉で云えば「コスパの悪い」仕事であると知っていたからであろう。 ちなみに、当サイトは、恥ずかしながら、いまだに「ホームページビルダー11」で作成しているのであるが、なんと天下の「日本IBM」製。20年くらい前のソフトなのに、まだまだ動く。現在のパソコンにもインストール出来る。さっすが〜〜。 という訳で、「売れているモノも売れているが故に売れなくなる」という話なのであるが、これ、当たり前すぎるからか、意外に気付いていない人が多い。むしろ、逆に考えている人が多い。すなわち、、「売れているモノは売れているが故に売れていく」。いや、売れねーよ。 これは、言葉を変えると、こうなる。すなわち、「社会が豊かになると、モノは売れなくなる」である。すなわち、「社会が豊かになると、売買活動が沈静する」、すなわち「社会が豊かになると、景気が悪くなる」、すなわち「社会が豊かになると、お金の流通量が減る」、すなわち「社会が豊かになると、お金が要らなくなってくる」である。「完全に豊かな社会はお金が不要になる」といっても良いであろうが、多くの「完全に」同様、この場合の「完全に」も不可能であろうから、それはない。その直前の「社会が豊かになると、お金が要らなくなってくる」。 でも、これ多くの人が逆に考えてんだよね。すなわち「社会が豊かになると、景気が良くなる」、あるいは「社会が豊かになると、お金が沢山必要になる」と考えている。分かり易いのが「GDP」で、あれを多くの人は「豊かさ」の指標と考えているけど、逆だよ。「貧しさ」の指標だよ。「貧しさ」から「豊かさ」へと移行する際に「GDP」は増していく。ヨーロッパ、アメリカ、日本、韓国、中国、インド、皆同様だよ。では、現在、アメリカのGDPが世界第1位なのは何故か。ちゃんと理由がある。後述しよう。 また、日本に限らず、多くの国の政治家、選挙云々抜きにしても、「景気回復」をマニフェストにする。そうして、多くの有権者は、まさしくバカの一つ覚えで「景気を回復して貰いたい」という。 で、当選した政治家はマニフェストを実行すべく「景気回復」に勤しむ訳であるが、現状その政策はただひとつ「ケインズ政策」しかない。減税や公共事業、金利調整、お金そのものの製造等々でこの世にお金をバラまくのである。 では、そのお金で「豊かな国の人々」はモノを買うだろうか。買う訳はない。だって、モノは溢れているのだから。先に私は「最近の人はクルマを複数台所有している」みたいな事を書いたけれども、複数台といったって、それはせいぜい2,3台である。よほどのカーキチでない限り、どれだけお金を持っていたとしても、100台200台とは買わないであろう。いや、よほどのカーキチだって、1万台1億台と所有することは無いであろう。いや、持つの?。 また、同様に、どんなにカツ丼が好きだと言っても、1度に1000杯も2000杯も食う人はいない。せいぜい、2,3杯が限度であろう。 また、豪邸に住む事を多くの人が夢見るけれど、仮に100部屋ある家を購入したとしても、実際に生活で使用するのは、2部屋ぐらいで、3部屋は物置、残りの95部屋はドアも開けたことが無い部屋となるであろう。人間っていうのはそういうものである。一日一部屋づつ、ローテーションして部屋を使っていく人間なんて、いない。いや、いるの?。 「立って半畳、寝て一畳」とはよく言ったものである。そういえば、最近、「マイケル・ジョーダンが家を売りに出して、なかなか売れなかった」というニュースがあったけど、そんなもんである。豪邸だって、持て余すのである。 事程左様に、人間の物欲というのは、心理的物理的、あるいは胃袋的に、どうしたって上限がある。「人間の物欲に上限が無い」と仮定しているところに、「ケインズ政策」の過ちの根拠がある。人間の物欲に上限が無ければ、成程、政府のバラまいた「お金」を人は使い続け、売買活動が活発になり、景気は良くなるであろう。でも、そうはならない。人間の物欲に上限があるから。でも、物欲に上限が無くても、景気は良くならないかもしれんけどな。 では、モノを買う事に使われない「お金」は何に使われるだろうか。それはもう、たった一つ。「お金」を買う事に使われるであろう。100万円で120万円を買おうとするである。1000万円で1億円を買うとするのである。すなわち、商売、投資、投機等々である。これらはみな同じ活動である。「投資と投機は、似て非なるものです。」なんていうのは完全なバカの発言だからな。これらはみな広い意味での「投資活動」、「お金を金で買おうとする活動」である。そうして、それらは皆例外なく「ギャンブル」である。ただ、賭けの対象が「サイコロの目」であるか「この冬の流行」か「流行りの株」か「人気の上昇する土地」かの違いでしかない。 まあ、勿論、純然たる「投資」、見返りを全く求めない、その業務が拡大伸長する事のみを望む「投資」も無くは無いが、これはまた別の話である。 で、「ギャンブル」というのは、「皆が持ち寄ったお金を少数が独占する事」であるから、そこに「貧富の差」が生まれる訳である。そうして、そこで金持ちになった人たちは、先述した通り「欲しいモノが無い」から、あらゆるものを高値で買う。すなわち「インフレ」である。この文章の冒頭のフアン・ソトのようなプロスポーツマンの給料の高騰も、そのひとつであろう。欲しいモノが無いから、プロスポーツチームを、一種の投機目的で買うのである。 一方で、各政府は、お金をばらまいても、人はモノを買わないので、消費税、所得税、法人税等々、各種税金として回収できず、いまや先進国の自治体名物となっている「財政赤字」となる訳である。「貯金」に税金は掛けられないでしょう。税金を巻き上げるとしたら、先に述べた「投資活動」からであろうけど、もともとお金を増やすための投資活動に多額の税金を掛けたら、本末転倒なので、それも出来ない。投資活動で得た儲けの95%に税金を掛けられたら、誰も投資活動なんてしないでしょ。 それ自体を楽しみにしているモノ、例えば、タバコや酒、クルマに掛ける税金とは訳が違う。タバコは95%の税金でも吸うでしょう。まあ、それを「中毒」というのだけど。 つう訳で、「貧富の差」「インフレ」「財政赤字」というのは「ケインズ政策」の当然の帰結なのである。で、それがいま最も強烈な形で露わになっているのがアメリカという訳である。そうして、「投資活動」はGDPに計上されるので、アメリカは「豊かな国」なのに「GDP世界一」になっている訳である。まあ、日本もアメリカの轍を突き進んでいるけどな。もっとも、今のアメリカみたいになる頃には、私はもう死んでるだろうから、僕知〜〜らないっと。 ちなみに、「財政赤字」はともかく、「インフレ」と「貧富の差」があるので、多くの貧しい人々が苦しむように思われるかもしれないが、そんな事はない。なぜなら、「豊かな社会」だから。この議論の一切の前提である。多くの人が必要なモノをほとんど持っている社会だからである。貧しい人を助けるのは政府が、それこそ「景気対策」の一環として、積極的にやるだろう。しかも、衣・食・住は余っているのである。売れなくて困るほどある。貧しい人に分け与えるくらい、どって事ない。 今の日本がそうでしょう。食料廃棄、空き家問題、リサイクルショップの盛況、衣食住、その他のものも皆余ってる。 むしろ、こういう「豊かな社会」で困るのは「貧」ではなくて、「富」の方である。お金を腐るほど持っていても、その使い道が無いのである。ポール・アレンなんか、その代表例で、お金を結局使いきれずに死んでしまい、遺産は慈善団体行き(貧者が富者から「タダ取り」した訳である。)となったそうである。晩年は恐らく、貧しいながらも夢中になってコンピューターをいじってた若い頃を死ぬほど懐かしんでいただろう。 実際、お金も1億円や10億円程度ならともかく、1000憶円5000億円となると、なかなか一人で個人的に使いきれるものではない。 仮にそのお金を世の中のために使おうとしても、この規模になると個人ではどうにもならない。 たとえば、アメリカの水道は水を直接飲めないので(いや、飲めるの?)、直接水が飲めるように改修整備したいと思い立つ。資金はある。腐るほどある。 でも、実際にそれをやろうとしたら、各種自治体と協議せねばならないし、議会との折衝、さらには衛生面での認可等々、「政治活動」を強いられる。大昔の王様のように、「やれ」の一言で完了しないのだ。 また、そこまで公共事業的でなくとも、例えばアメリカの東西、更には南北に高速鉄道を敷きたいと思い立っても、水道ほどでないにせよ、なんらかの「政治活動」は必須となってくるであろう。 「お金を使う」も、ある規模を超えたら、個人の思惑・行動だけでは完結しないのだ。これらに比べると、スケールはだいぶ小さいが、ホリエモン騒動なんか、その一例であろう。堀江は、カツ丼やジーパン、クルマ、株券を買うように、バファローズやフジテレビを買えると思っていたのだろう。まっ、若いからしょうがないか。 ポール・アレンやホリエモンの悪口を書いてしまったけれど、実際、「お金を使う」というのは「お金を集める」よりはるかに難しい。「お金を集める」というのは、「あらゆる商売はギャンブル」である以上、「運」次第でどうにでもなる。「強運」に恵まれれば、とんでもない大金を手に入れる事ができる。そういう人達は、いつの時代も山ほどいる。 ところが「お金を使う」、とりわけ「大金を使う」は完全に能力である。才能である。それも非常に希少な才能である。ましてや、「大金を正しく使う」なんて、世界史上に数人レベルの話である。 そういった意味では、ある程度の大金の投資や運用は、個人ではなく、政府とまでは云わないが、なんらかの公的機関が担うべきだと思う。 そう言えば、こんなのをYouTube番組で見た。若い女性が、昨今の投資ブームに乗って、投資を検討しているのであるが、「絶対損したくないんです。どうしたらいんですか。」と、ファイナンシャルプランナー(要するに、「投資素人」)に相談すると、「それは分散投資しかありませんね。リスク分散ですよ。」。 リスク分散なら、銀行に預けるべきだよね。そうして、銀行はその預金をどのように運用するか、財界や通産省と相談し、財界はこれから伸びそうな産業を提案する。すると、通産省は、それにまつわる法整備をすすめ、見事その産業は成功する。そうして、その預金に利子が付き、預金者に還元される。 このスキームが、ものの見事にハマったのが戦後の日本なのであるが(つかまあ、どこの国も似たような事してるけどさ。)、その成功っぷりが悔しくて、アメリカはそれを「護送船団方式」として非難、80年代以降から、我々日本人は「個人投資」を推奨される訳である。「財テク」なんて言葉もあったよね。 話はちょっと戻るが、「景気が良くなる」状態を正しく作る方法は二つしかない。無論、「ケインズ政策」ではない。 一つ目は「欲しいモノだらけになる事」。分かり易く言えば、「戦後の日本」である。これは、当然「モノの売買が盛んになる」ので「景気は良くなる」。 これは不謹慎な話になるが、東北大震災の際に似たような事を述べたバカがいたけれど、あの程度の災害(被災者の皆様、ごめんなさい。)では、景気は良くならない。 「景気が良くなる」レベルで「欲しいモノだらけ」になるには、それこそ太平洋戦争級、第2次世界大戦級の戦争が必須となるであろうが、「景気を良くする」為に戦争をするなんていうのは、完全な本末転倒であるから、無意味な仮定である。 二つ目は「欲しくなるようなモノを作る事」である。これの最も分かり易い事例は、それこそ先のパソコン革命インターネット革命であろう。多くの人々がパソコンを欲しがり、パソコン業界は景気が良くなった訳である。所謂「ITバブル」である。 この手のもの、時代や地域で規模の差こそあれ、色々あるであろう。ファミコン、テレビ、自動車、香辛料等々である。シューペンター謂うところの「イノベーション」である。 こちらは、一つ目と違って、非常に平和的であるけれど、大きな問題が一つあって、それは「欲しくなるようなモノが分からない」である。先にも話した通り、何が売れるかなんて誰にも分からないのである。例えば、スマートフォンだって、それの発表当初、「こんなもの売れねーー。」って宣った人がそこそこいたくらいなのである。ちなみに、私は、「セーラームーン」や「ミニ四駆」の時とは違って、「これは売れる」と思った。「こんな商品を待ってた」と思った。「そのうち、こういう商品が現れる」と思ってた。自慢する訳じゃないけどな。 スマートフォンを「売れない」と思った人を責める事は出来ない。それくらい、「何が売れるか」は誰にも分からんのだ。例えば、「タント」という軽自動車も、発表当初は自動車評論家諸氏から、「こんなもん、売れねー。」と酷評されていたのであるが、結果は大ヒット。トールワゴンというジャンルを構築する程の大ヒットとなった訳である。 でも、この自動車評論家諸氏は責められない。それくらい、「何が売れるか」は誰にも分からんのだ。 てな事は、どーでもいいんじゃ〜〜〜〜い。 今最も重要なのはイースタンカンファレンス・ファイナルなんじゃ〜〜〜い。 この第3戦から第5戦、ペーサーズ側から見て●○●の1勝2敗。開幕2連勝しているので、通算は3勝2敗。残る2戦、ひとつでも勝てばファイナル進出となる訳である。 その辺の話は後回しにして、とりあえず、10年振りのプレイオフ観戦の感想をば。 前回も同じことを書いたのであるが、シーズン中は3P大会だったにもかかわらず、プレイオフに入るとインサイドを強調してくる。そうして、それはプレイオフが深まるにつれて、悪化、というか、より強調されるようである。 どんだけ統計学的に強調されても、いざとなれば、ついついゴールに近づいてしまうのが人間の心理、というか人間としての、あるいは動物としての本能なのであろう。 昔、テレビのドキュメンタリー番組でアフリカのどこぞの部族の槍名人を放送してた。槍名人といっても、陸上競技のように、その投擲距離を競う訳ではなく、動物を射るのである。ハンティングとか釣りみたいなものである。まあ、アフリカの部族といっても、実際に槍で猛獣を撃退したり、食用として動物を射っているのかは分からない。「ショー」あるいは「伝統芸」として、槍を使っているだけなのかもしれない。 その辺の真偽はともかくとして、スタッフがその槍名人に問う。「槍で動物を射るコツは何ですか。」。んで、その解答はというと、「んじゃのう。出来るだけ近づく事じゃ。」。 で、実際、動物に1メートルぐらいまで近づいて、槍を射ってやんの。 「颯爽と大草原を走る牛や鹿を、20メートルくらい離れた所から、槍で射貫く」といったようなマンガみたいな映像を予想していた私はズッコケた。それ「槍名人」じゃなくて、「気付かれずに動物に近づく名人」だろ。 まっ、そんなもんだよね。それが人間の心理、動物の本能である。「モノを投げる際には、目的にできるだけ近づく」である。 その槍名人に倣ったかは知らぬが、NBAもプレイオフになると、「3P統計学」はかなぐり捨てて、インサイドプレイヤーもアウトサイドプレイヤーも皆一様に、ゴールに向けてドライブしとる。 いや、いんだけどさ。シュートが決まれば、それでも。でも、みんな決まらんのよね、これが。そりゃそうだよ、レギュラーシーズン中は3P大会してんのに、いきなりドライブ大会じゃ、上手くいかなかろう。「普段していない事は、大事な時にも出来ない」である。 特に笑っちゃうのが、センター陣で、ターナーもタウンズも一緒になってドライブしてやんの。しかも、トップ・オブ・ザ・キーから。いや、それPGの仕事だろう。センターにやらせる仕事じゃねーだろ。 最近はローポストが禁じられているらしいので、センターといえども、ペイント内で点取るためにはペネトレイトせざる得ないのだろうけど、にしてもである。 前回も書いたけど、ペイント内のオフェンススキル、最近の選手、皆無だよね。オラジュワンやシャックと比較するのは可哀想だけど、リック・スミッツと比べても、ペイント内のオフェンススキルは劣るように思う。まあ、オスタータグやロングリーと比べてどうかと云えば、微妙なところだろうけど。 そうして、インサイドプレイヤーは無論の事、アウトサイドプレイヤーもペイント内のオフェンススキルがヘタッピなんだよね。ポストプレイはともかくとして(マーク・ジャクソンの特技!!!)、ドライブも下手なんだよな。ペネトレイトして、困ったらフローターかフェイダウェイなんだけど、フローターはともかく、そのフェイダウェイの「高さ」が無い。ジョーダンやコービーに比べると、全然低い。まあ、別に「高さ」が全てという訳でもないけど、とりあえず美しくはない。 また、デリック・ローズのように「強さ」がある訳でもないから、パスを捌けるわけでもない。とりあえずのキックアウトである。 んで、ケビン・ジョンソンやティム・ハーダウェイのような「速さ」がある訳でもない。 つう訳で、インサイドプレイヤー、アウトサイドプレイヤーともにペイント内のオフェンススキルが皆無であるにも関わらず、ひたすらゴールに近づこうとするので、結果、無様な不格好な不細工なバスケットボールになってる。「最近のNBAはつまらない」という声が出るのも、このバスケットボールではやむを得ないであろう。とりあえず、美しくない。 「個人のスキルが無いなら、チームオフェンス」でという方法も無くは無いけど、それなら、とりあえず「プリンストン・オフェンス」の採用という事となる。かつてのキングスが見せたような美しいバスケットボールである。ただ、そんなチーム、私の少ない知見の範囲では、現在のNBAには無い。いや、あるの?。 こういうのを見てると、メジャーリーグのプレイオフによく似ていると思う。レギュラーシーズンはホームラン合戦をしているくせに、プレイオフに入ったら、スモールベースボールをしようとして醜態を晒すアレである。 「普段していない事は、大事な時にも出来ない」。 って、こういう風に書くと、この言葉をそのまま受け取って、「普段してない事は、大事な時にもしない」と解釈するバカがいる。この場合で云えば、「プレイオフに入っても、3P大会、ホームラン合戦を続けろ」という事になるが、違うからな。逆だからな。 「普段していない事は、大事な時にも出来ない」から、「普段から、大事な時に必要な事をしておけ。」って意味、教導だからな。かつて、全盛期の西武ライオンズが日本シリーズで使うプレイを春季キャンプの段階から練習してたってのは、そういう意味だぞ。逆の意味にとるなよ。 でもまあ、今、スポーツに限らず、こういう人は本当に多いんだよね。 「普段していない事は、大事な時にも出来ないから、やらない」って人。以前、どっかで書いたが、私の大嫌いな言葉に「出来る事から、始めよう」というのがあるけど、これ、完全な欺瞞の言葉だからな。これは「出来ない事は、やりません」って言ってるのと同義だからな。人間は「やるべき事を、出来るようにしよう」だろう。「出来ない事を、出来るようにしよう」だろう。ライト兄弟を、スティーブ・ジョブスを、大谷を見ろ。 っつても、現状のNBAのプレイヤーは、先に書いた通り、ペイント内のオフェンススキルが皆無であるから、すなわち「出来ない事は、出来ない」から、3Pに頼るしかないと思う。統計的にも正しいんだしね。現状の「無暗なペネトレイト」は、ほんと無価値無意味だと思う。実際、3Pの成功率や成功数で勝敗は決してるしね。大差のつく試合が多いのは、そういう理由だと思う。3Pの成功率は、結局は「調子」、すなわち「運」だからな。どちらかに偏ってしまうと、大差がついてしまうのだろう。 んで、それを嫌がって、より確実な得点方法、すなわち「ペイント内」を求める訳だけど、先述した通り「ペイント内のオフェンススキルが皆無」であるから、結局3P頼み、運頼み、無様な不格好な不細工なバスケットボールになってしまう。結果、以下省略。 でも、アメリカ人も変わったよね。一昔前のアメリカ人はこういう安直な事、浅知恵な事は絶対しなかった。万端に準備してた、周到に用意してた。日本人もそうなるんだけどな。 各試合評は省略。上記のような理由で、あんま書く事がない。 選手評だけ。 やはり、ミッチェル・ロビンソン。第3戦からスターターで使ってきたな。スタッツが伸びたって訳でもないけど、チームは2勝1敗。グググ。 そのロビンソンであるが、前回「3P無し」って書いたけど、よく考えたら、キャリア7年で、いくらインサイド専門とはいえ、「3P無し」はねーだろ。 今の時代どころか、一昔前だって、そんな」奴いねーよ。たとえば、シャックとかユーイングだって、シーズンに1回くらいは、クォーター終わりとかガベージタイムとかで、遊びで3Pを打つだろう。それが0って。メイクはともかく、アテンプトも0って。「絶対3P打たない教」の信者か。それとも「3P打ったら死んじゃう病」の患者か。いや、欲しい。ホシイ。 んなとこか。これから数時間後、運命って程でもないけど、第6戦、チップオフ。 死んでも勝て〜〜〜〜〜〜。 やると思ったでしょ。やるんですよ。 2025/6/1(日) |
|
| 第6戦 5月31日 NYN@IND 108−125 |
っしゃあ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜。 ペイサーズ、25年振り、ファイナル進出決定〜〜〜〜。 時間が無いので、取り急ぎご報告まで。 いや、もうちょい書くか。 しかし、25年振りか。子供のころ、1985年の阪神優勝の「21年振り」というのが、えらい昔、太古の昔のように感じていたのだけど、それを超える「25年」。でも、そんなに昔には感じない。さすがに「昨日の事のように」って事は無いが、あれから25年か。私も年を取ったのう。25年間、それなりに色々ありました。 でも、NBA観戦復帰した途端に「ファイナル進出」とはね。まあでも、私の人生、そういう事多いのでそんなに驚きません。「応援し始めると、優勝しがち」なのである。 とはいえ、あまり感動はない。現今のペイサーズには何の思い入れも無いからだ。知らん選手もまだいる。 あと、そう言えば、前回書き忘れたが、スパイク・リーが姿を見せてましたな。地球追放じゃなかったみたい。存在を消去されてなかったみたい。第3戦、第4戦、第5戦は確認したけど、第6戦は確認してない。かつてほど、テレビカメラがその姿を抜かないので、私が目を離した時に画面に映ってたのかもしれん。派手なカッコしてた。素っ頓狂レベルのファッション。 あと、第6戦のゲインブリッジ・フィールドハウス(昔、なんつー名前だったけ。忘れちった。)のモニターでパット・マカフィーのパンター時代の映像が流れてた。甘やかすなよ、パット・マカフィーを。チヤホヤするなよ、パット・マカフィーを。釘を刺しとく。 で、ファイナルはオクラホマシティとの対決。究極のカッペ対決。「シティ」とか「ポリス」とかつく地名は露骨に田舎臭いよね。今、ウィキでちょいと調べたら、オクラホマ州もインディアンのための州だったらしい。同族か。 っしゃあ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜。 2025/6/2(月) |