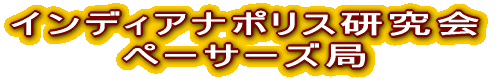

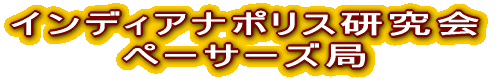


| Finals | 6月5日 IND@OKC 111−110 |
長嶋茂雄が世を去った。 年齢が年齢であるし、こういう事はあまり言いたくないが、病を得て老いていく長嶋を見ていて辛いという気も無くは無かった。ビーチたけしの言う通り、「来るべき時が来た」という事なのだろう。 今回の長嶋の死に対して、当然のことながら多くの人がコメントを残した。その中でも最もショックだったのは、中畑の「俺の方が先に死にたかった」であろう。同じような気持ちを抱いた人は少なくなかったと思う。 私は、本来、あるいは原則的に人の死に対しては淡白な方である。「命は必ず死ぬ」という気持ちは常にある。故に、幼児の死であっても、それほど心は動かされない。運命だと思う。 故に、という訳でもないけど、野村克也や鳥山明の死にも、それほど心が動くことは無かった。訃報に接しても、ちょっと目頭が熱くなるくらいであった。 ところが、今回は、その死の当日、 仕事中に、ふと長嶋の事を想い、涙を流してしまった。同僚に見られなくて本当に良かった。しかも、私は派閥的には野村派であり、長嶋派とは対立派閥である。 そういう人なのだと思う。最近、バラードの記事で「GM論」を論った際に、「広岡は会う人会う人全てに嫌われた。広岡を嫌わなかった人はいない。」みたいな事を書いたけれども、長嶋はちょうどその逆なのであろう。 どんなスーパースターでも、例えばマイケル・ジョーダンのようなスーパースターでも良く思わない人はいる。いや、ジョーダンの場合は嫌っている人の方が多いくらいかな。でも、長嶋の事を嫌っている人、悪く言う人は聞いたことが無い。野村や王にしたって、長嶋はあくまでライバルであり、嫌っている訳ではない。まさしく、「長嶋は会う人会う人に好かれた。長嶋を好きにならない人はいない。」。 そうした対人関係的には両極にある二人が史上最高とも評される三遊間を組んでいたのは面白いところである。 さて、長嶋の事跡を振り返ってみるに、それを一口で云ってしまえば、「ミラクル」であろう。それに尽きると言ってもよい。最近では「持ってる」なんて俗語があるけれども、そんな軽々しい俗語では表現しきれない程の「ミラクル」に彩られているのが長嶋の人生、と云ったら大袈裟だけど、長嶋茂雄の野球人生ではある 私はかつて長嶋の三大ミラクルについて書いた事があったけれども、それにまたいくつか付け加えたい。 長嶋の第1のミラクルといえば、それは、申す迄も無く、あの「4打席連続空振り三振デビュー」である。 でも、これ、その「4打席連続空振り三振」の派手さのみが語られがちだけど、よくよく考えてみると、デビュー戦の対戦相手が金田正一、すなわち後の史上最高の投手400勝投手の金田正一の、それも全盛期であるって事が、まず第1のミラクルである。 杉下でも秋山でも小山でもなく、金田だったって事が、まず第1のミラクルである。単純計算なら11分の1、セントラルリーグに入団したという意味では5分の1だけど、それでも金田を引き当てるのが長嶋茂雄の強運、ミラクルである。 実際、その後にも、こういう事例はないんだよね。「超大物ルーキーが史上最高の選手、とまではいかなくとも、現役最強選手といきなりぶち当たる」というのは、これが唯一の事例だと思う。松坂vs片岡では、松坂はともかく片岡のスケールが小さすぎるし、松井vs石井一久はオープン戦だし、石井はこの時点では全盛期では全然ない、ただのペーペーだし。 強いて挙げれば、野茂vs清原だろうけど、清原のキャリアはあんな調子だし、またこの時点における現役最強バッターは誰がどう考えても落合だし、次点は門田であろう。長嶋vs金田と比較すると格落ち感は否めない。ちなみに、ここで挙げた事例は、みな三振という結果に終わっている。初対決ではピッチャーが圧倒的に有利であるというのは、こういう点からも分かる。 それはともかく、こういうところで金田を引き当てるのが長嶋の長嶋たる所以であろう。王の756号の時の鈴木康二朗とはえらい違いである。鈴木康二朗の事を悪く言うつもりは無いけどさ。 じゃあ、誰が良かったのかといってもパッとは思いつかない。松岡や平松でも格落ち感は否めない。強いて言えば、山口騠志だろうけど、パシフィックリーグだし、この時点では、既に全盛期ではなかった。 あともうひとつ、無理目の仮定としては、江川であろう。江川がこの時点でどこかセントラルリーグのチームに入団し、王に756号を打たれていたら伝説になっていたろう。このへんが長嶋と王の決定的な違い、引きの強さの違いである。 そうして、その金田との対決は、皆さんご存じの通り「4打席連続空振り三振」。 これも、派手さだけが語られがちだけど、異常な事だと思う。なぜなら、たいていの野球選手は2打席連続空振り三振を喫したら、3打席目は当てに行く、あるいはボールを見ていくであろう。少なくとも「空振り三振だけはしない」というバッティングになる筈である。 というか、キャリア10年20年の選手でも「4打席連続空振り三振」の経験のある人はほとんどいないのではないだろうか。張本や落合、イチローのようなタイプが「4打席連続空振り三振」するなんて事はほぼ無いであろうし、野村や王、田淵のような典型的なホームランバッターでも「4打席連続三振」はともかく、「4打席連続空振り三振」は無いのではないだろうか。ブライアントとか晩年の清原、あるいは海の向こうのシュワーバーあたりは喫しているかもしれない。あと、そうそう、小早川が例の「開幕戦3ホーマー」の翌日のゲームで4打席連続三振をしていたと思う。「お前は長嶋茂雄か。」とツッコんだ記憶がある。「4打席連続空振り三振」だったかは記憶にない。 なのに、長嶋はプロ初打席から堂々と「4打席連続空振り三振」。自身がラインナップから外れるなんて、微塵も考えていない。しかも、長嶋がブライアントやシュワーバーのような「三振かホームランか」という様な選手ならともかく、そのシーズンは打率2位、つかあわや三冠王の選手である。異常としか言いようがない。 そうして、長嶋ミラクルの頂点「天覧試合のサヨナラホームラン」。これはもう奇跡としか言いようがない。 これは以前にもどこかで書いたが、この「天覧試合」は単なる天皇陛下がご観戦なさったゲームではない。昭和34年の話である。終戦後(敗戦後)14年目の話である。このペイサーズのファイナル進出が25年前である。子供はともかく、大人にとっての25年なんて、悲しいかな、そんなに昔の話ではない。まして、14年なんて、多くの大人にとっては昨日の事の、まさしく昨日の事のように戦争を記憶しているであろう。 実際、プロレスの世界では日米ともに「アメリカ人vs日本人」のアングルが大当たりをとっていた時代である。「日本人、ぶっ殺せ〜〜。」「アメリカ人、ぶっ殺せ〜〜。」の時代である。 そうした時代に、実質的にはともかく、公文書的には太平洋戦争の首謀者である昭和天皇が、敵性娯楽の野球をご覧になるというのである。この重さ、今となっては実感しにくいものであろう。 そこでサヨナラホームランを放ち、昭和天皇に身を乗り出させたのが、長嶋茂雄なのである。今の若い人はともかく、私から上の世代はその映像を1000回はともかく100回は最低でも見ているであろう。そうして、合成されたあの写真。これを奇跡と呼ばず何と呼ぼう。 そもそも、サヨナラホームランを打つためには乗り越えなければならないハードルがいくつもある。まず、当たり前であるが、同点あるいはリードされている状態で9回裏を迎えねばならない。9回表で勝つ訳にはいかない。そうして、当然ながら裏の攻撃でなければならい。表の攻撃では絶対サヨナラホームランを打てない。そうして、それらを乗り越えて自身に打順が回って来なければならない。それは単純計算だと3分の1の確率である。で、最後に、当然ながらホームランを打たなければならない。 天文学的とまでは云わないけど、かなり微小な確率である。そうして、それを天覧試合でやってのけたのが長嶋茂雄なのである。究極のミラクルといってよいであろう。 ちなみに、長嶋の通算サヨナラホームランは7本。決して多い方ではない。ちなみに、王は8本。これは少なく感じるかもしれないが、当然「敬遠」もあるし、前後のバッターとの絡みもあるので、数の高下のみで優劣は決められない。ちなみに、亀井は通算101ホームランで7本、阪急の矢野は64本で6本。バッターの力量と直接には関係ない数字ではある。ハウエルのように1年で5本打つ選手もいるしね。 それはともかく、その7本のサヨナラホームランのうち1本を長嶋は天覧試合で放っているのである。そうして、天覧試合はこれが最初にして最後なのである。ちなみに、日米野球で一度天覧試合があるのだが、長嶋はこちらでもホームランを打っている。サヨナラではないけど。 天覧試合というと希少な感じはするけれど、決して特別少ない訳ではない。昭和天皇に限らず、皇族が御観覧になるスポーツは数多くある。「天皇杯」の冠のつく競技も多い。また、昭和天皇の相撲好きは有名であるし、実際、ほぼ毎場所のように御観覧なさっていたと思う。 ところが、プロ野球を昭和天皇が御観覧なさった公式戦は、これただ一つなのである。そもそも、そんなに野球には興味が無かったのかもしれないし、太平洋戦争に関する政治的ご配慮もあったかもしれない。 そのたったひとつの「天覧試合」でサヨナラホームランをかっ飛ばしてしまったのが長嶋茂雄なのである。そうして「天覧試合」といえば、昭和天皇に限らず、多くの皇族による御観覧が数多くあるにもかかわらず、何はともあれ、これ、長嶋茂雄の「天覧試合」なのである。というか、他の「天覧試合」は誰も覚えていない。「麒麟児と富士櫻」ぐらいか。ちなみに、麒麟児も千葉県出身。昭和天皇は千葉県民と相性がいいのか。 ちなみに、ここで長嶋がホームランを打った相手、すなわち長嶋茂雄にホームランを打たれたのはルーキー、村山実。後のミスター・タイガースである。こういう点でも、長嶋はミラクルなのである。 また、ちなみに巨人の先発は藤田、阪神は小山である。藤田は前年の国鉄との開幕戦、すなわち「4打席連続空振り三振」の試合の先発でもある。監督交代の一件といい、長嶋とは因縁のある男である。さしずめ、「長嶋の影」といったところか。 このへんは長嶋の1年目2年目の話であるが、ルーキーイヤーのミラクルといえば、その他に「あわや三冠王」と「あわやトリプルスリー」が有名であろう。 「あわや三冠王」の方は、シーズン終盤に首位打者争い恒例の「出る出ない」をやらずに2位に終わったと言われている。それはともかくとして、注目すべきは「あわやトリプルスルー」の方であろう。当時は「トリプルスルー」という栄誉そのものが無かったのは残念至極であるが、それを「ベース踏み忘れ」で逃すというのが長嶋の数あるミラクルのひとつであろう。そんな選手いる。そんな事ってある。 また、長嶋の1年目2年目で忘れられがちなのは日本シリーズ2連敗というのがある。1年目は、あの「神様仏様稲尾様」、2年目は杉浦の「4連投4連勝」に敗退する訳である。したがって、試合的な勝敗は3連勝からの8連敗となる。 んで、3年目は「三原マジック炸裂」でリーグ優勝も逃す。かくして、長嶋茂雄初めての日本一は4年目の「円城寺 あれがボールか 秋の空」まで待たねばならない。 長嶋というと、「チャンスに強い男」や「V9」のイメージがあるため、日本シリーズに強いイメージがあるが、初の日本一は意外にも4年目なのである。もっとも、その後、日本シリーズで敗退する事ないまま引退する訳ではあるが。 でも、こうやって、改めて見てみると、長嶋の入団以来最初の4年間の日本シリーズは球史に残るものばかり、とりわけ最初の3年間は、そのまま「日本シリーズ・トップ3」に選ばれてもおかしくないような日本プロ野球選手権シリーズだった訳である。 これは長嶋とは直接関係ないけれども、日本のプロ野球が日の出の勢いで人気を獲得していった一因ではあろう。これらと軌を一にするというのも、長嶋のミラクルのひとつではある。 そうして、V9。こちらの真の主役は、どちらかといえば、王であろうが、長嶋も無論、この立役者の一人である。 このV9も、なんだかんだ言って、「ミラクル」なんだよね。なかなか破られない。これに最も近づいたのは、80年代90年代の西武ライオンズであろうが、ブーマーの三冠王や神様仏様バース様、そうして何よりブライアントの4振りによって妨げられ、最長V3止まり。 そもそも、V9に次ぐのがセ・パ分裂後ではソフトバンクのV4が最長で、V9の半分にも届かないっていうのだから、その異常性、ミラクルの程が分かろう。 仮に、西武やソフトバンクのように戦力的に充実したとしていても、「選手の高齢化」や「ちょっとした運不運」、そうして何より「モチベーションの維持の難しさ」があって、V3V4あたりが限界なのであろう。アメリカのメジャースポーツだと、ヤンキースのV5、カナディアンズのV5、セルティックスのV8が最長。 運不運の要素の比較的少ないバスケットボールでさえV8が最長だから、V9が尋常でない難事業、ミラクルである事が分かろうものである。 で、選手生活最後は、あの「我が巨人軍は永久に不滅です」。この日本史上もっとも有名なスピーチ(次点は玉音放送)、当時は人口に膾炙し、今は大分廃れたが、70年代80年代には盛んに引用、パロディされた。澁澤龍彦にも、「女のエピソードは永遠に不滅です。」なんて一文がある。間違えてんだよね〜〜。「永遠に」じゃないんだよね〜〜。「永久に」なんだよね〜〜。これも澁澤に限らず、盛んに間違えられた点である。 普通に考えれば、「永久に」より「永遠に」の方がカッコ良さそう、文学的であろうけど(前者は「科学的」かな。)、そこに「永久に」を用いるのが長嶋の長嶋たる所以、長嶋独特の言語感覚というものであろう。いわゆるひとつの〜、「永久に」ですね。 そうして、この言葉の意味するところは、当時から謎であったし、今でも謎である。当の長嶋本人にも分からないであろう。この言葉についての長嶋自身の感想批評は聞いたことがない。 ちなみに、この引退スピーチに関しては元々原稿があったと言われている。読売新聞社だか日本テレビだかが企画して、小学生ぐらいの子供たちを集め、長嶋本人と話し合いながら、稿を推したらしい。「昭和33年に入団し、天覧試合で〜、栄光のV9が〜、」みたいな原稿を作成していたのであろう。 ところが、あの場に立った長嶋茂雄は一切を忘れてしまい、「我が巨人軍は永久に不滅です」となったそうである。意味を問うだけ無駄というものであろう。 もっとも、その後、いや、その前もかな、多くの選手が引退セレモニーや引退スピーチを行ったが、誰もこの長嶋の一語に遠く及ばない。アメリカには、ゲーリックの「私は地球上で最も幸せな男です。」があるけれども、これは長嶋の一語とは類を異にするものであろう。 ただ、日本はともかく、昨今のアメリカのプロスポーツマン事情を鑑みると、この言葉もいくらか重みを帯びてくる。意味を得てくる。今現在、この言葉を引退スピーチで用いる資格のあるプロスポーツマンはアメリカに何人いるであろうか。パッと思いつくのはステファン・カリーぐらいである。トラウトやジャッジは、まだ資格を有しているが、今後は分からん。大谷はとっくに資格を失っている。レブロンは、論外。 ちょっと前には我らがレジー・ミラーを始め、ダンカンやジーター、バリー・サンダース等々、それなりにいた。それも今や大変な希少種である。 長嶋も、現役時代はともかく、浪人時代(長嶋にのみ使用された言葉)は、大洋やヤクルト、あるいは地元の千葉ロッテと、監督を噂された。 でも結果的には、ジャイアンツに操を立てた。これについては賛否両論あろうが、多くの長嶋ファンは、やっぱりジャイアンツ以外のユニフォームに袖を通す長嶋を見たくは無かったろう。そういった意味でも、長嶋は非常に優れたプロ野球選手、ミスター・ベースボールではなく、ミスター・プロ野球だったと思う。誰から教わる事も無く、長嶋茂雄はプロスポーツというものを知っていた。知悉していた。 で、引退後は、元スーパースターとして余生を送るのかと思いきや、そうはいかないのが、長嶋の長嶋たる所以である。出るわ出るわ、トンチンカンなエピソードの数々。私より下の世代にとっては、「カッコいいプロ野球選手としての長嶋茂雄」より「面白エピソード製造機の、天然を超えた天然としての長嶋茂雄」の方が印象強いであろう。 最も有名なのは「一茂置き去り事件」であろうが、この真偽を問われた一茂は、「一度や二度じゃないよ、しょっちゅうだよ。いや、ほぼ毎回だよ。係の人に言われたからね。『また、忘れられたの。お前、長嶋さんに嫌われてんじゃねーの。実の子じゃないとか。』。」。 また、納会だか春季キャンプだかで、長嶋以下数人の選手が大部屋で就寝していると、深夜、長嶋は起き上がり、トイレだか素振りだかに向かう、その時、黒江曰く、「あの人、全員、踏んでいくんだよ。いや、むしろ、踏む方が難しいだろ。わざとやってんのかと疑ったよ。」。 また、大学時代、杉浦曰く、「同級生がシゲだよ。毎日、説教だよ。同じ過ちを際限なく繰り返すんだもん。で、連帯責任なんで、俺たち全員正座、説教、そして、ビンタ、ないしゲンコ。でも、シゲはケロッとしてて、次の日も同じ過ちを繰り返すんだよ。最後は先輩が諦めてたからね。『俺の拳の方が壊れる』って言ってた。」。 また、90年代、モツ煮が流行ってた頃、長嶋もハマっていたらしい。で、行きつけの店があり、「大将、こんちわ」みたいな感じで入店すると、出入り口すぐ近くのカウンター席という有名人が絶対座らない席に、せっかちな長嶋は座り、「大将、おでん」。大将も分かっていて、「モツ煮」を出す。無論、この店のメニューに「おでん」はない。長嶋は「大将、このおでん、いつも旨いね〜。」と言って、5分ぐらいで平らげると、すぐ店を出てってしまう。無論、お代は払わない。大将も最初は当惑したらしいが、巨人軍に連絡すると、言い値で支払われた。長嶋の買い物は基本的にこのシステム(?)らしい。確かに「我が巨人軍は永久に不滅です」じゃないと困るよな。巨人軍が潰れたら、長嶋の経済活動も潰れてしまう。連鎖倒産。 と、軽く4つ紹介してみたけど(3つにすべきだったか。)、この手の話が、それこそ無限にあるのが長嶋茂雄である。長嶋が生きている限り、量産される。 ちなみに、私が好きなのは、ロスアンジェルス・オリンピックの時の「カール、カール」かな。ロス五輪の主役の一人を強引に呼び止め、インタビューしていた姿が懐かしい。カール・ルイスもこの長嶋の訃報は知っただろうから、懐かしんでるんだろうな。「あのおっさん、死んだのか。」。 プリティ長嶋よりも長嶋茂雄本人の方が面白い。モノマネ芸人より本人の方が面白いという、おそらく唯一の事例であろう。 そのファニー長嶋も理由のひとつであろうが、日本のマンガに最も多く登場した実在の人物は長嶋茂雄であろう。ギャグマンガ的なモノにも数多く登場しているし、シリアスものも数多い。その筆頭は、なんといっても「巨人の星」であろう。その冒頭から登場する。 そうして、その「巨人の星」をアンチテーゼにした「男どアホウ甲子園」にも冒頭から登場し、最後、ラスボス的な位置付けでも登場する。長嶋が登場するマンガは数多いけれど、最も重要な役割で登場するのは、この「男どアホウ甲子園」だと思う。唐突感は否めなかったけどな。 と、引退後の長嶋のオモシロ側面のみをフィーチャーしてしまったけど、無論、ジャイアンツの監督としても活躍、はともかく、変わらずミラクルしてる。 一年目の、巨人史上初めてというか、現時点でも唯一の最下位が、まずいきなりミラクルである。いくら長嶋が抜けたとはいえ、王のケガがあったとはいえ、2年前の優勝チームが最下位なのである。忘れがちであるが、ミラクルといってよいであろう。堀内監督でさえ、5位だからな。 で、その翌年が、その最下位からのいきなり優勝である。で、日本シリーズでは3連敗から3連勝して最終戦、しかもホームの最終戦を落とすというミラクル。ちなみに、第6戦はサヨナラ勝ち。しかも、5回表終了時点で0−7のビハインドからのサヨナラ勝ち。そんな事ある。これ、あまりフィーチャーされないけど、かなりなミラクルだと思う。 で、第2次の時は例の「10.8」。もっとも、これもシーズン中ずっと鍔迫り合いをしての最終決戦ならともかく、8月くらいで巨人の優勝が決定的と言われた段階から、ズルズル負けを重ねての最終決戦なので、あまり威張れたものではない。むしろ、あの展開で最終戦を落とした中日の方が、1976のジャイアンツ同様、マヌケだったと言えなくもない。まあでも、日本プロ野球史上唯一の最終決戦であることは間違いないので、やはりミラクルといえよう。 んで、最後の「ON対決」。監督のライバリーとしての日本シリーズという意味では、「三原・水原」「野村・森」に次ぐものであろうが、監督としての力量がこの2組と比較すると、いかにも落ちるので、日本シリーズそのものはしょっぱかったと思う。とはいえ、「ON」という、日本プロ野球史上最高のコンビにして最高のライバルの対決が最後の最後で実現したという意味では、まさしく長嶋茂雄最後のミラクルだったと云えるであろう。 プレイヤーとして、あるいは野球人として、強烈なライバルが、監督として日本シリーズで対決したのは、なんだかんだで、これが唯一の事例だと思う。「三原・水原」は、因縁はあったけれども、プレイヤーとしてそこまでのライバルではないし、「野村・森」もキャッチャーとしてはともかく、プレイヤーとしての格は野村の方がはるかに上なので、ON級のライバルとは言えないであろう。ON級は、あとはもうKKぐらいしかないと思う。監督として、日本シリーズで対決するのは、ほぼ不可能だろうけどな。そういった意味では、「ON対決」は、非常に稀有な、ミラクルな対決だったと思う。内容はともかく、看板的には。 また、世界的に見ても、これが唯一の事例ではないだろうか。現役時代のライバルが、監督あるいはHCとしてチャンピオンシップを争うというのは、これが唯一の事例だと思う。 「マジックvsバード」は結局実現しなかったし(今後、あるかもしれんけど、)、「ディマジオvsテッド・ウィリアムズ」も無いし、「メイズvsマントル」も無い。無論、「ルースvsゲーリック」も無い。 もしかしたら「クライフvsベッケンバウアー」はあったのかもしれないが、私はサッカー事情には疎いので、真偽は不明。 という訳で、「ミラクル」に彩られたのが長嶋茂雄の球歴なのであるが、こういう選手は、当然のことながら、日本にはいない。また、先の監督対決同様、世界的に見ても珍しいのではないだろうか。私はヨーロッパのスポーツシーンはほとんど知らないので、その判断は留保させていただくが、アメリカのスポーツシーンにおいては、似たような選手はいない。他のプロ野球選手、王や金田、あるいは落合や清原、イチローや松井のような選手は、メジャーリーグや、他のアメリカプロスポーツの世界にいる。野村は、似たようなのがいないかもしれないが、今後出てくる可能性はある。 また、地位的には、ベーブ・ルースやモハメド・アリ、マイケル・ジョーダンと同等であろうが、彼らは、あくまで自身の力量、スポーツマンとしての実績、人格的な魅力等々も含めて、自身の力でその地位を獲得したのであり、長嶋の事跡に特徴的にみられるような「ミラクル」ではない。 「キンシャサ」がミラクルといえばミラクルと言えなくも無いが、「アップセット」はスポーツには付きものの現象であるし、長嶋的な「ミラクル」とは言えないであろう。また、この手の「ミラクル」というのは、「キンシャサ」に限らず、「ノースカロライナ・ステイト」等々、その大部分はプレイヤー自身の力で引き寄せたものであり、長嶋のような「巡り合わせ」や「運命」といった「他力」を感じさせるものではない。 例えば、上記の「天覧試合」にしても、サヨナラホームラン自体は誰でも打つ力そのものは持っているであろう。王にしても野村にしても、落合にしても清原にしても、松井や大谷にしても、サヨナラホームランを打つ能力自体は、長嶋と同等、あるいはそれ以上であろう。でも、その場にいたのは、やっぱりはっきり長嶋茂雄なのである。そうして、そこでサヨナラホームランを打ってしまうのが、長嶋茂雄なのである。王は、その場に最も近いところにいた、謂わばニアミスしたけど、やっぱりはっきり王にはバッターボックスは回ってこないのである。その試合、王もホームランを打っている。ONアベックホーマー第1号。 同じような事は、上述した「4打席連続空振り三振」にもいえよう。自身のデビュー戦に金田正一、全盛期の金田正一を引き寄せてしまうのが長嶋茂雄なのである。 大谷の二刀流に特徴的にみられるように、多くのスポーツマンの事跡(いや、他の世界でも同様かな。)は、「できるできない」の話である。そうして、「できた」人達が、大谷であり、マイケル・ジョーダンであり、モハメド・アリであり、王貞治なのであろう。 ところが、長嶋茂雄の事跡は違うのだ。「できる・できない」ではなく、「ある・あらぬ」の話なのである。「可能性」の話ではなく、「蓋然性」の話なのである。似たような選手は、いない。 「ミラクル」自体は誰にでも起こるものであろう。起こらなければ、「ミラクル」ではない。実際、起こる人はいる。日本のプロ野球で云えば、近藤の「初登板ノーヒットノーラン」とか、北川の「逆転サヨナラ優勝決定満塁ホームラン」などは、その類のものであろう。でも、それは彼らに一度しか起きなかった。それはそうであろう。一度しか起きないからこそ、「ミラクル」なのである。 ところが、長嶋茂雄の事跡は、その「ミラクル」が連続するのだ。そこに、長嶋茂雄の特異性があり、長嶋茂雄の「ミラクル」がある。こんな選手、いない。二人目が現れたら、「ミラクル」でなくなってしまう。いや、それこそ、「ミラクル」か。 マイケル・ジョーダンは「神」に例えられるが、それはすなわち、マイケル・ジョーダンが、あたかも「神のように万能」だからであろう。他方、長嶋茂雄は、「神に最も愛されたスポーツマン」と云える。 それ故、アメリカ人のやる事を何でも真似る日本人が「GOAT論争」を出来ないのである。もし、長嶋茂雄がいなければ、アメリカ人同様に、史上最高の選手は、金田なのか、王なのか、野村なのか、イチローなのか、大谷なのか、喧々諤々したであろう。また、他のスポーツ、釜本や松尾、双葉山や大鵬、青木、尾崎等も含めて、喧々諤々した事であろう。でも、出来ない。長嶋茂雄がいるから。彼等には、長嶋茂雄のような「ミラクル」がないから。 実際、長嶋茂雄がいなければ、「GOAT」であったろう王貞治が、そんな不満を漏らしている。「僕がどんなに頑張っても、僕は常に2番手、ナンバー2なんです。ナンバー1は長嶋さん。長嶋さんが兄で、僕は弟。その関係は永遠に変わらないんですよ。」。長嶋の、ほぼ倍もホームランを打っているのにねえ。 そういう選手がすぐ隣にいるっていうのが、これまた長嶋の「ミラクル」なんだよねえ。普通は、いない。そんな偶然、ない。 ちなみに、そういう長嶋の「ミラクル」を除いた、純然たる野球選手としての能力はという、勿論非凡なものでは絶対ないけど、近い選手は色々といる。「パ・リーグの長嶋」と言われた有藤とか、「長嶋後継者レースの勝者」である原とか、秋山(初代)とか、最近では山田とか、要するに「圧倒的な運動能力で結果を出す」タイプである。 その中で、最も近いのは同郷の後輩、掛布であろう。「江川との初対決でホームラン」とか「オールスターの3打席連続ホームラン」とか、「1985年のタイガースの立役者」であるとか、ちょっとした「ミラクル」もあるし。 ちなみに、各都道府県別で作る「オール千葉」は結構スゴイ。三塁手は、長嶋の控えが掛布で、掛布の控えが古屋。ファーストは、小笠原の控えが谷沢で、谷沢の控えが福浦。ショートは、石毛の控えが宇野。セカンドは、篠塚の控えが和田。キャッチャーは阿部で、外野は、高橋、丸、近藤と、なかなかの陣容である。ピッチャーは、右が木樽、左が石井一久かな。重要な選手を忘れていたら、ゴメンナサイ。 「オール○○」なら、どこの都道府県でも似たような陣容になるんじゃないかとも思われる方もいるかもしれないが、同じ関東でも、千葉の反対側「オール神奈川」は結構しょっぱい。「3番田代、4番原」みたいな陣容である。で、最多安打が井端みたいな感じ。と思ってたら、柴田がいた。神奈川出身の名球会は、この柴田と、ピッチャーの山本だけかもしれん。 同じような事は、埼玉、群馬、栃木、茨城にも言える。この中では、茨城が比較的豪華かな。 おそらく、東京が関東では最も豪華なのだろう。「3番田淵、4番王」みたいな陣容である。んで、王の控えが榎本である。ピッチャーは、土橋、成田みたいな感じかな。 日本で最も人口の多い関東でも、こんな調子なので、他の都道府県だと、有名選手で先発を埋めるのも難しいかもしれない。野球の盛んなイメージの強い四国各県も案外苦しみそうである。 逆に、最も強そうなのは大阪、愛知という事になり、それに続くのが広島、兵庫、京都、熊本といったあたりになるだろう。東京、千葉はそれに続く第3グループぐらいじゃないかな。こういう点から見ても、野球は西日本のスポーツだというのが、よく分かる。広島の外野なんか、張本、山本、金本だからな。広瀬や柳田が控えだからな。 もっとも、実際に都道府県別対抗トーナメントを開いたら、「オール岩手」が楽々優勝してしまうだろう。なにしろ「4番ピッチャー大谷」だからな。ガチ「4番ピッチャー」だからな。王も野村も勝てないよ。なにしろ、メジャーのホームラン王だからな。秋山も蓑田も山田も勝てないよ、メジャーの50−50だからな。 もっとも、その「オール岩手」、つうか大谷に「ミラクル」を起こして、長嶋が勝ってしまうかもな。 とまあ、「ミラクル」「ミラクル」と書き続けてきて、今更こんな事を云うのもおかしいだろうが、長嶋茂雄の真の魅力は「ミラクル」にあるのではない。長嶋の真の魅力は、「カッコよさ」にあるのだ。 長嶋はカッコイイからスーパースターになったのである。「スポーツマンがカッコイイなんて当たり前の話じゃないか。」と思われる方もいるであろうが、カッコいいスポーツマンというのは案外いないものである。皆無に近いといってよいかもしれない。金田でも王でも野村でも張本でも落合でもイチローでも野茂でも清原で、そうして大谷もカッコよくは無かった。アメリカも同様である。マダックスでもボンズでも、マジックでもレブロンでも、マニングでもマホームズでも、カッコよくは無かった。 私がリアルタイムで見た選手でカッコよかったのはただ一人、マイケル・ジョーダンのみである。 それは恐らく長嶋茂雄でも同様であろう。私は長嶋のプレイをリアルタイムでは見ていない。でも、江夏にこういう証言がある。「長嶋さんとの初対決は今でも覚えているよ。ツーベースかスリーベースを打たれたんだよね。で、長嶋さんがベースにスライディングするんだけどさ。カッコよかったんだよね。テレビなんか持ってなかったから、それが初めて見る『動く長嶋茂雄』だったんだけど、一発で好きになっちゃった。なるほど、これが天下の長嶋茂雄か。ファンになっちゃった。惚れ惚れした。」。 同じような事はマイケル・ジョーダンにもよく言われる。敵の選手へのアドバイス、というか注意として「マイケル・ジョーダンに見とれるな」「Don't stop looking at M.J」。 長嶋茂雄とマイケル・ジョーダンは、単にホームランを打ったり、単にダンクを叩きこんだ訳ではない。長嶋茂雄とマイケル・ジョーダンは、カッコよくホームランを打ち、カッコよくダンクを叩き込んだのだ。長嶋は、カッコよくエラーもしたけどな。 そう、長嶋茂雄は、マイケル・ジョーダンは、カッコよかったのである。一挙手一投足がカッコよかったのである。そのミラクルでもなく、その実績でもなく、カッコよかったから、スーパースターになったのだ。 長嶋茂雄の命日は3日。雨の日だった。 長々とご清聴(ご清読?)ありがとうございました。 まあ、長嶋の死だからねえ。日本に生まれて、スポーツが好きで、長嶋の死に遭遇したら、何か書いちゃうよねえ。何も感じない、何も考えないなんて有り得ない。 日本に生まれて、マンガが好きで、鳥山明の死に遭遇したら、なんか書いちゃうのと同じ。って、こっちはまだ書き途中だけど。 野村の死に遭遇した時は何も書かなかったけど、これは当たり前。書く事が山ほどあるからじゃ〜〜〜。これから、書くわ〜〜い。っていうか、野村の死に遭遇しなくても、書いてた。 以上かな。って、以上じゃないわ〜〜い。この稿のタイトル「ファイナル第1戦」だったわ〜〜い。 っしゃあ〜〜〜〜〜〜〜〜。 他は次回。ちゃんちゃん。 2025/6/8(日) |
| 第2戦〜 第4戦 |
茂雄の葬儀の喪主は三奈でしたな。ま、さすがに一茂じゃな。かつて、ナンシー関が一茂を「永遠の小学生」と称していたけど、小学生に喪主は無理ですな。 でも、三奈は懐かしい、かつて、私は三奈が好きだった。いや、狙ってた。「どうにかならんかなあ。」と思ってた。 だって、義理とはいえ、茂雄が父親になるんだぞ。そんな女、他にいねーだろ。家に茂雄がいんだぞ。そんな特典、他にねーだろ。まあ、一茂が義兄になるという大きなマイナスポイントも無くは無いが(正興はどこに行った。)、そこは目を瞑ろう。我慢する。 もちろん、「マスオさん」だよ。当然、ムコ養子だよ。実の両親なんて、ペッペだよ。お前ら、近づくな。苗字なんて、速攻変えるわ。長嶋○○になるわ。う〜〜ん、麗しい響き。んで、住所は田園調布。田園調布玉川じゃないからな。 実際、三奈を超える女と云ったら、あとはもう愛子様しかねえ。 ただまあ、こちらは仮に上手くいったとしても(いや、そんな「仮に」は無いけどさ。)、完全なる生活の保障、完全なる人生の保障、完全なる余命の保障を得る代わりに、いろんなものを失うからなあ。エロ本一冊買えない人生になるからなあ。考えもんだぞ。熟慮に熟慮を重ねないと。 美智子皇太后や雅子皇后も、当然のことながら、相当悩んだらしいしね。なかでも雅子皇后は、かなり活発な人だったらしいから、その悩みも深かったろう。 こういう議論になると、必ず「皇室も、もっとフランクに」なんて発言が出てくるのだが、「皇室があまりフランクになられてもなあ。」というのもある。フランクで無くてこその「皇室」であろう。イギリスのロイヤルファミリーを見ていると、「ありゃ違うだろ。」つう気持ちもある。報道関係も含めてね。 そう云やあ、美智子皇太后の御結婚騒動の時に、確か深沢七郎だったと思うけど、「1500年もかけて作ったウラナリに、今更野生の血を混ぜんな」という発言があった。この発言の賛否はともかくとして、その後の皇族の顔付きを知った今となっては、この「1500年のウラナリの血の濃さ」が分かろうというものである。二人くらい野生の血を入れても、ウラナリは全然変わらん。1500年かけて作ったものは1500年かけないと元には戻らんのかもしれん。 はっ、もしかしたら、エロ本買ってんのか。皇族でもエロ本は買えるのか。今上天皇は美少女フィギュアとか好きそうだもんな。世代的には、ガチヲタク世代、というか1960年生まれなので、真正オリジナル元祖ヲタク世代である。秘密の部屋とか、あるのかもしれん。んで、それを愛子様が発見して、雅子皇后に報告。それを雅子皇后はひとしきり悩む。実際、清子内親王はヲタクっぽい人だったらしいしね。いや、愛子様はBLか。BLなのか。 でも、そういう方が、皇族、日本の貴族としては、正統な趣味、ウラナリの正統な趣味という気もする。所謂「たおやめぶり」やね。 こういう事書いてっと、それこそ右翼に殺されるかもしれないので、この辺にしとこっと。 と言いつつ、もひとつ不謹慎なことを書いちゃう。 先日、つか、ずっとだけど、イスラエルとイランの間でミサイルの応酬があった。この両国の政治問題について、私に発言する資格、能力は無い。また、興味もない。ただ、私がこのニュースで、ちょいと思ったのは、「最近のミサイルって、殺傷力が低いんだな。」って事である。ね、不謹慎でしょ。 イランから100発ほどテルアビブに向けてミサイルが発射され、そのほとんどが迎撃され、9発が着弾したらしいのだけど、私の知る限り、死者は7名のみ。 いや、被害を受けた方々にはお悔み申しますけど、ご冥福をお祈りいたしますけど、9発着弾して7人しか死なないって(いや、不謹慎をお詫び申し上げます。)、性能悪過ぎじゃないの。いやまあ、これから増えるのかもしれないけどさ。 私の母親は戦中派であり、所謂「空襲」経験者であるのだが、その母の言葉によれば、空襲後は死体の山、神社の境内に、それこそ山積みにされていたらしいのであるが、それに比すると、現代のミサイルは殺傷力が低過ぎると思う。同じ事はロシア・ウクライナ戦争でも感じた。現代兵器は殺傷力が低過ぎる。 いやまあ、それこそ、国の存亡を賭けた、それこそ「一億総玉砕」の太平洋戦争と、中近東や中央アジアでの小競り合いは、その規模とか、何より覚悟が全然違うかもしれないけれど、昨今の兵器は殺傷力が低過ぎない。ビルとかも破壊しきれてないし、「焼野原」とは程遠い感じ。 いや、そういう風に作ってんの。人道的配慮から、あまり人が死なないような兵器(?)にしてんの。焼夷弾は禁止してんの。それは喜ばしき事、歓迎すべき事、慶すべき事だろうけどさ。でもそれじゃあ、太平洋戦争、第2次世界大戦がバカみたいじゃん。 その昔、「大戦略」というシュミレーションゲームをやってたら、「市街地爆撃」というミッションがあって、テレビゲームとはいえ、手が震えた。この爆弾を落とすと、多くの命が、家庭の幸福が、市民の人生が失われる。 さて、そんな不謹慎な話はともかくとして、NBAファイナルである。 ここまで4戦を消化して、2勝2敗。星取表は、ペイサーズ側から見て○●○●ときれいに並んでる。残り3戦で完全決着じゃ〜〜。 とまあ、上手い具合に実力伯仲、戦力均衡している訳であるが、第何戦だったか忘れたが、この点についてテレビ放送で触れていた。このファイナルの星取表はともかくとして、この6年間、すなわち2017,2018のウォリアーズ以降、連覇が無い。それも、それぞれ6チームが優勝していて、重複も無いという話題である。 それを受けて、日本の実況席の解説者は「NBAの戦力均衡政策が機能している」みたいな話をしていたけど、私はそうは思わない。いくらか力を発揮しているかもしれないが、それは微力だと思う。 なぜなら、それ以前、すなわちこの6年間以前から、ドラフトもサラリーキャップも施行されているからだ。サラリーキャップは最近いくらかハードになったらしいけど、それでも決定的な力は発揮していないと思う。NFL流のハードキャップを施行しても、大きな差は無いと思う。 ドラフトやサラリーキャップはNBAの「戦力均衡」にはあまり役に立っていないと思う。というのも、、サラリーキャップ施行以前、すなわち70年代は現在同様、優勝やファイナル進出チームはバラけているからだ。一方で、60年代80年代はセルティックス・レイカーズ時代。サラリーキャップの施行された90年代以降は、ブルズ、スパーズ、レイカーズ、ヒート、ウォリアーズ等々、5年周期くらいで優勝チームが入れ替わっている。そこに連覇が散りばめられているといった様相であろう。 この理由は何故かといえば、ひとつには「ロースターが少ない」という点であろう。野球はおよそ25人、フットボールはおよそ50人というロースターでチームを構成するのに比して、バスケットボールはおよそ15人。オン・ザ・コートが5人で、ローテーションを含めても10人くらいが必須人数である。選手を維持する、チームを維持するのは、野球やフットボールより容易い。「例外条項」がなくとも、あるいはNFL的なハードキャップであっても、戦力維持は野球やバスケットボールより容易いであろう。 まして、バスケットボール、あるいはNBAは「ナンバー1プレイヤーのいるチームが勝つゲーム、あるいは勝つリーグ」である。運良くナンバー1プレイヤーを入手出来たら、とにかくそのプレイヤーを確保し続けて、他のプレイヤーは何とかするで、どうにかなってしまうスポーツ、リーグなのである。ジョーダンがいれば、グラントがロッドマンに代わっても優勝できるし、ダンカンがいれば、エイブリー・ジョンソンがトニー・パーカーに代わっても優勝できる。コービーがいれば、シャックがガソルに代わっても、かは分からん。自粛自粛。無用な論争は避けよう。 かくして、ドラフトやサラリーキャップという制度は、野球やフットボールほどには効力を発揮しないのである。「NBAはスーパースターがいないと勝てない。NFLはスーパースターがいても勝てない。」。 また、別の理由としては、野球やフットボールに比して、「運の要素が少ない」というのもあろう。室内競技であるから、天候の影響は受けないし、野球のように球場の広さがそれぞれに異なる訳でもない。で、ボールも丸い。勿論、リムやバックボードの跳ね返り具合とかレフェリーの判定、選手のケガ等々といった「運不運」も無くは無いけれど、野球やフットボールより、「運不運」ははるかに少ないであろう。 以上二つが、NBAが、NFLやメジャーリーグに比して、「強いチームがそのまま勝つ」、更には「連覇がしやすい」理由のほぼ全て、というか全部だと思う。 では、70年代はともかく、ここ5年くらいは、何故に優勝がバラけるのか、強いチームがそのまま優勝できないのか。 それはやはり、戦術の変化が大きいと思う。これだけ、3P大会はともかくとして、オフェンスが外角からのシュート中心となると、どうしても運不運に左右されがちになる。運不運の要素が強くなる。結果的に、強いチームがそのまま勝てない、優勝がバラけてしまうのであろう。 その最も分かり易いというか、その恩恵を最も受けたチームが、他ならぬ、今季のペイサーズであろう。その象徴が、東地区決勝第1戦のハリバートンの決勝シュートであり、ファイナル第1戦のマイルズ・ターナーのバンクショット3Pであろう。 いやまあ、技術かもしれんよ。「リムやバックボートの跳ね返りを計算してシュートしたのだ」と強弁されたら、こちらは最終的には反論できないけど(実際、「決まった」からな。)、でも偶然でしょ、あんなの。そんなややこしいシュートを打たずに、普通にスイッシュしろって話だよ。 こういうプレイ的な運不運もあるし、調子的な運不運もあろう。実際、今プレイオフのペイサーズは第4クォーターにうまい具合にシュートが決まり、勝利を得たゲームが多い。いやまあ、第4クォーターでシュートが決まるようにゲームデザインしたと強弁されたら、最終的にはそれに反論できないけど、普通はそんなゲームデザイン、ないっしょ。タマタマだと思わざる得ない。 実際、このシュートの調子、外角からのシュートの調子、すなわち「運不運」が。今プレイオフの各チームの勝敗を決していると思う。その調子の差が前半で顕れちゃうと、「大差のゲーム」になるし、ペイサーズのように第4クォーターの勝負所で顕れれば、「派手な逆転劇」となるのだろう。 で、この5年くらいは、その外角のシュートの調子、すなわち「運の良かった」チームが優勝しているのだと思う。バラける訳である。運不運に偏りはあるけれど、それ自体は平等だからだ。 では、何故、それ以前のチームは運不運に左右されなかったか、強いチームがそのまま勝ったのか、連覇が多かったのかといえば、それはすなわちペイント内の得点力が高かったからである。ペイント内の得点、とりわけダンクやレイアップは運不運に左右されない。 実際、80年代以降の強いチーム、ナンバー1プレイヤーは全てインサイドプレイヤー、ペイント内の得点力に長けたチーム、プレイヤーばかりである。「セルティックスの史上最強のフロントライン」、「ジャバーのスカイフックとマジックのローポスト」「オラジュワンのドリームシェイク」「ダンカンのファンダメンタル」「シャックアタック」等々である。 「では、ジョーダンは、」となるだろうけど、ジョーダンは、そのシュートの多くがダンクやレイアップ、ダブルクラッチである。それらがあってのフェイダウェイである。すなわち、インサイドプレイヤーなのである。ジョーダンというのは「史上初めてのインサイドプレイヤーのガード」なのである。コービーはそのダウングレード・バージョンといったところであろう。故に、シャックやガソルを必要としたのだ。 そういった意味では、「ペイント内のオフェンスを制限する」というルール変更は「戦力均衡」に大きな効力を発揮したと言えるであろう。ウォリアーズとステファン・カリーは、見てないのでよく分からん。この問題をどう解決したのだろ。「時代に一歩先んじた」って事だったのかな。スティーブ・カー畏るべし。さすがにジョーダンに食って掛かった男だけの事はある。 つう訳で、昨今のチーム(いや、今季、それも後半しか知らんけどさ。)は皆一様に「ペイント内のオフェンススキル」が皆無に等しい訳であるが、その中になって、ちょっと趣が違うのが、このサンダーである。このチームには「ペイント内のオフェンススキル」がある。センターやフォワード陣には、他チーム同様、それは無いのだけれど、ガードにある。すなわち、シェイ・ギリジャス=アレキサンダー、SGAにある。 このアレキサンダーは、昨今のガードと違って、ペネトレイトしても、ちゃんとダンクやレイアップでフィニッシュできる。で、それらがあるからフェイダウェイも活きる。フローター頼みのハリバートンとは、そこが決定的に異なる。 で、このSGA、「誰かに似てんな〜。」と思ったのであるが、それが誰だか全然思いつかなかった。「密集を抜けるのが上手いから、バリー・サンダースかな。」とか訳の分からん比較をしてた。そしたら、1週間ほどして、仕事中にハッと気づいた。ようやく分かった。リップ・ハミルトンである。このペネトレイトのスタイル、リップ・ハミルトンによう似とる。 リップ・ハミルトン・クラスの選手がMVPというのが昨今のNBAのレベルだとも言えなくはないが、まあ、そのリップ・ハミルトンも優勝してるしな。 でも、そのリップ・ハミルトン、じゃなかった、SGAの分だけ、すなわちペイント内の安定した得点力がある分だけ、サンダーは他チームより強いとは云える。このファイナルの戦前、サンダー有利の声が多かったのは、それが理由であろう。私も同じ予想をする。 実際、今のペイサーズ、ファイナルに出てくるようなチームにはとても思えないんだよな。一昔前、すなわち私が観戦していた10年前くらいまでは、ファイナルに出てくるチームというのは、「なるほど、ファイナルに出てくるな。」、その理由がはっきり分かるチームばかりだった。先にも述べたように、バスケットボールは運不運の要素が少ないからだ。 でも、今季のペイサーズ、ファンの私が云うのもなんだが、完全に運だよな。運良くファイナルに進出したとしか思えない。最近のファイナルはこんな感じなのだろうか。 で、そのツイてるペイサーズの象徴、ニスミスであるが、確かに思わぬところで思わぬ活躍をするので、目立つ、印象深い選手だけど、オフェンス、ディフェンスともに、とてもスターターレベルとは思えない。「よく使うな」というのが、私の感想である。実際、第4戦でのファウルは致命傷になったしね。かといって、マサリンも似たようなもんだしなあ。強いて言えば、シェパードか。いや、よく出て来たな、このチーム。 でも、泣いても笑っても、あと3戦である。運でもなんでもいい。 死んでも勝て〜〜〜〜〜〜〜。 2025/6/15(日) |